はじめに:認知症と口座凍結の問題
認知症は、人々の生活に深刻な影響を及ぼす病気です。
特に、金融面での自己決定能力の喪失は、個人の経済活動に大きな障害となります。
認知症によって判断力が低下した場合、金融機関は口座凍結という手続きを取ることがあり、これにより患者の日常生活に必要な資金へのアクセスが制限されることがあります。
このような状況は、患者本人だけでなく、その家族にとっても大きな負担となります。
したがって、認知症の進行に伴う経済的リスクを理解し、適切な事前対策を行うことが極めて重要です。
この記事では、認知症と口座凍結の関係について詳しく解説し、その影響と対策について考察します。
認知症患者とその家族が直面するこの問題に対し、具体的な解決策を提案することで、安心して生活できる社会の実現に貢献します。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しております。
▼▼この記事を書いた人▼▼
詳細はプロフィールをご覧ください。

運営者:すくらっち
【40代をスマートに】40代2児の父 | 金融サービスに従事。子育てしながら親の介護・資産管理もぼちぼち視野に入ってきたので熟考中。たくさんちしきをインプットして同じ年代、同じ悩みを抱えた皆さまにアウトプット中。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
金融機関は認知症だとなぜ分かるのか?
まずはこの疑問から解消していきましょう。

金融機関は親が認知症だとなぜ分かるの?

以下のようなケースです。
①家族が金融機関に伝える
②多額の出金があった場合
③不自然な出金が続いた場合
金融機関は出金記録やキャッシュカードの利用状況を定期的にチェックしているから
②、③のような状況はすぐに分かるようです。
金融機関は不正利用や不正アクセス防止の観点から不自然なお金の動きがあった場合、細かくチェックを入れています。
一方で、親に認知症の疑いがあったり認知症の進行が進んだ場合、生活費や介護で周囲の家族が本人に代わってキャッシュカードを使うということは容易に想像できますね。
介護する家族も、いつか金融機関からお金が引き出せなくなると考えて手元に置いておいた方がという発想になります。
これが多額の出金や不自然な出金となって表れるのです。
認知症が進行した場合の経済的リスク

認知症が進行すると、患者は自らの財産を管理する能力を徐々に失います。
この能力の喪失は、経済的自立性に直接影響を及ぼし、患者の生活資金へのアクセスが制限される可能性があります。
金融機関は、認知症患者の判断力が低下していると判断した場合、口座凍結という手続きを取ることがあります。
これにより、患者は日常生活に必要な資金の引き出しや、医療費、介護費用の支払いが困難になることがあります。
主なリスクとしては、以下のようなものがあります。
口座凍結
認知症患者の判断能力が低下すると、金融機関はその人の口座を保護するために凍結手続きをすることがあります。
これにより、預貯金が動かせなくなり、日常生活や緊急時の支出に必要な資金にアクセスできなくなります。
医療費と介護費用の支払い困難
認知症の治療やケアには高額な費用がかかることが多く、口座凍結によりこれらの費用を支払うための資金を得ることができない場合、家族は経済的な負担を強いられます。
不動産の売却や管理の問題
認知症患者が不動産を所有している場合、適切な管理や必要に応じた売却が困難になります。
これにより、資産価値の減少や管理上の問題が生じる可能性があります。
生前贈与や相続計画の障害

認知症が進行すると、生前贈与や相続計画を行うことが難しくなります。
これにより、税金の面で不利益を受けることがあります。
さらに、認知症になると、詐欺や不利な契約から自身を守る能力が低下します。
例えば振り込め詐欺では、高齢者が家族を装った詐欺師に騙され大金を失うケースがあります。
このような詐欺は、認知症患者の判断力の低下と孤独感を利用しています。そのため、家族や社会のサポートが重要となるのです。
経済的リスクは、患者や家族の精神的な安定にも影響を及ぼすため、家族の財産を守るための計画を早期に立て、実行に移す必要があります。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
口座凍結の現実:認知症患者の金融アクセス

口座凍結は、その口座を持つ本人だけでなく、その家族にも大きな影響を及ぼします。
生活費や医療費の支払いが困難になることで、家族は経済的な負担を強いられることになります。
また、本人が自由に金融取引を行えないことで、社会的な孤立を深める原因ともなり得ます。
このような状況を防ぐためには、認知症の診断を受けた初期段階で、家族信託「おやとこ」の設定など、事前対策を行うことが重要です。
家族信託を利用することで、信頼できる家族が患者の代わりに財産を管理し、必要な資金へのアクセスを確保することが可能になります。
認知症患者の金融アクセスを確保することは、患者の尊厳と自立を支えるために不可欠です。
家族が協力して事前対策を行うことで、口座凍結のリスクを最小限に抑え、患者が安心して生活できる環境を整えることができます。
事前対策のステップと家族信託のメリット
親に認知症の疑いがある場合、いつ口座凍結が行われてもおかしくありません。
「金融機関は親の認知症をなぜ分かるのか?」でお伝えした通り、金融機関の判断で急にそのタイミングが訪れてしまうのです。
家族信託の事前対策は、将来の不確実性に備えるための重要なステップです。
「おやとこ」のような家族信託のサービスを利用することで、認知症が進行した後に成年後見制度に頼るしかなくなる前に、家族が自分たちにあったサービスについて話し合い、後々、家族が財産管理を行う対策をすることができます。
早期対策
認知症の進行前に対策をすることで、家族が直面するであろう経済的なリスクを回避します。
平穏な家族関係
財産管理に関するトラブルを未然に防ぎ、家族間の平穏を保ちます。
迅速な対応
緊急時に迅速に資金を動かすことができます。

【家族信託「おやとこ」の準備ステップ】
①家族会議の開催
家族全員で将来の財産管理について話し合い、信託の目的と計画を明確にします。
②信託契約の作成
専門家と協力して、家族のニーズに合わせた信託契約を作成します。
③信託財産の選定
管理する財産を選定し、信託に移す手続きをします。
④信託管理者の指名
信頼できる家族信託管理者を指名し、その役割と責任を理解させます。
⑤定期的な見直し
定期的に信託の内容を見直し、必要に応じて更新します。
家族信託の事前対策は、家族の未来を守るための重要な一歩です。
家族信託を利用することで、認知症の進行に伴う経済的なリスクを最小限に抑え、家族の安心と安定を確保することができます。
認知症が進行する前に、家族信託の準備や手続きを行うことは、家族の経済的な安全と心の平和を守るために不可欠です。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
まとめ:安心のための行動計画
いかがでしたか?高齢の親を持つ家族にとって、事前対策は将来への安心をもたらします。
家族信託を含む行動計画を立てることで、口座凍結のリスクを減らし、親の財産を守ります。
家族が協力し、患者の意志に沿った財産管理を行うことは、親や見守る家族の安心につながるのです。
未来に向けて、家族が一致団結して認知症患者の経済的安全を確保することが、何よりも重要です。
家族の絆を深め、安心のための行動計画を立てましょう。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
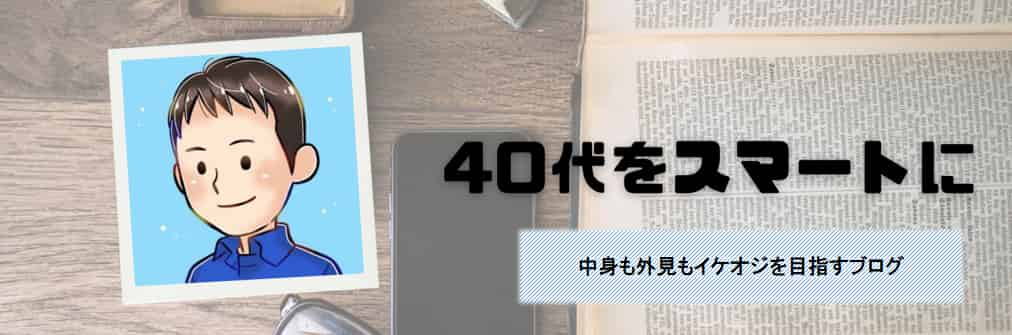


コメント