40代も半ばに差し掛かり、子どもの手がかからなくなる一方、新たな悩みの種が出てきました。
それは親の介護や財産の管理についてです。
きっかけはほんの些細な親の物忘れ。
ちょっと前に話した孫の運動会の日程を忘れてしまったようで、先日わたしに電話がありました。

あら?〇〇ちゃんの運動会っていつだったっけ?
このまえ聞いたような気もするけど。。。
ただの物忘れだったのですが、私の親も70代。年も年なのでそろそろ「認知症」も気にしなくてはならないと思いました。
40代で親が健在であれば皆さん同じような悩みをお持ちなのではないでしょうか?
「万が一の事態が起こってしまって介護をしなくてはならない」と考えたとき、介護の労力もさることながら一番心配なのはやっぱりお金の部分。。。

親の介護費用って誰が払うの?
子供が払うの?
兄弟みんなできっちり負担を分けられるかな?
やっぱり親の資産から介護費用を出すことはできないのかな?
多くの家族が頭を悩ませる問題ではないでしょうか?
適切な財産管理方法を選ばないと、親の生活の質が低下するだけでなく、家族全体にとっても大きな負担となります。
そこで、この記事では認知症の親の財産管理について、最も良い方法を探るためのポイントを詳しく解説します。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しております。
▼▼この記事を書いた人▼▼
詳細はプロフィールをご覧ください。

運営者:すくらっち
【40代をスマートに】40代2児の父 | 金融サービスに従事。子育てしながら親の介護・資産管理もぼちぼち視野に入ってきたので熟考中。たくさんちしきをインプットして同じ年代、同じ悩みを抱えた皆さまにアウトプット中。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
認知症の親の財産管理を考えなければならない理由
親が認知症になると、日常生活だけでなく財産管理にも大きな影響が出てきます。
認知症が進行すると、親が自身の財産を管理する能力が低下してしまいます。
パッと思いつくだけでも以下のようなリスクが発生します。
親が認知症になってしまったときのリスク
✅銀行口座からお金を引き出せなくなる
✅資産・財産・不動産の契約、解約が困難になる
✅資産・財産・不動産の契約変更が困難になる
✅詐欺の被害にあいやすくなる
✅必要な医療や介護を受けられなくなる
上記は親にとってのリスクに見えますが、子どもや親族にとっても大きな負担となります。
こうした状況を避けるために、早めに対策を講じることが大切です。
認知症の親のためにどのように財産管理を行うべきかを考えることはわたしたち家族にとっても非常に重要なのです。
親の財産管理の方法は大きく3つ
では、親に認知症の疑いがあるとき、認知症と診断されてしまったときにどのような財産管理の方法が存在するのでしょうか?
主な財産管理の方法として3つが挙げられます。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
認知症の親の財産管理方法を比較
認知症の親の財産管理について考えるとき、どの方法が一番適しているかを考えなければなりません。
それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、親の状況や家族の希望に合わせて選ぶことが必要です。
ここでは、主な財産管理の方法である任意後見制度、法定後見制度、そして家族信託について詳しく見ていきましょう。
財産管理の方法とは?
財産管理の方法にはいくつかの選択肢がありますので、それぞれの特徴を理解して最適な方法を選ぶために、まずは基本的な仕組みを知っておきましょう。
任意後見制度
任意後見制度は、親がまだ判断能力を持っているうちに、自分の財産管理を信頼できる人に任せる方法です。
親自身が契約によって後見人を指定するため、親の希望が反映されやすいというメリットがあります。
法定後見制度
法定後見制度は、親の判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任する方法です。
この制度は公正さが保たれ、親の利益を守るための仕組みが整っていますが、手続きが煩雑になることがあります。
家族信託
家族信託は、親の財産を信託として管理し、信頼できる家族がその管理を行う方法です。
財産管理の自由度が高く柔軟に対応できるため、最近注目されている方法です。
信託の契約内容に応じて、親の希望を細かく反映させることができます。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
任意後見制度の特徴とメリット・デメリット
任意後見制度は、親が認知症になる前に、信頼できる人(任意後見人)に将来的な財産管理を任せる契約を結ぶ制度です。
この契約は公正証書で行われ、親が判断能力を失ったときに効力を発揮します。
この制度のメリットとデメリットを見てみましょう。
任意後見制度のメリット
任意後見制度の大きなメリットは、親が自分で後見人を選び、将来の財産管理を計画できるので、親の希望や意向がしっかりと反映されます。
財産管理以外にも生活支援の範囲や方法を事前に合意することが可能です。
後見人に支払う毎月の報酬も契約によって自由に設定できるため、親族や近親者に依頼する場合、この費用を抑えられる可能性があります。
また、任意後見人は親の判断能力が低下した後も継続してサポートを行うため、長期的な安心感を得ることができます。
任意後見制度のデメリット
一方で、任意後見制度にはデメリットもあります。
まず、任意後見契約を結ぶためには親の判断能力が必要であり、認知症が進行してからでは遅いこともあります。
また、後見人の選定や契約内容に不備があると、親の希望通りに運用されない可能性があります。
第三者の後見人は費用が高い
後見人に親族以外の第三者を設定する場合も注意が必要です。
第三者の場合、弁護士や司法書士にお願いする形になると思いますが、やはり士業の方にお願いするとランニングコストが高いです。
後見監督人の選任が必要
任意後見制度では後見監督人の選任が必須で、一般的には弁護士などの専門家が就任するため後見監督人への報酬も発生します。
後見人と後見監督人は別。後見人の設定意外に後見監督人の設定も必要になる。
後見監督人の月額報酬は家庭裁判所で決定されますが、最低でも月1万、年間12万は必要になります。
任意後見人には取消権がない
たとえば、親(本人)がなんらかの悪徳商法に引っかかってしまい、高額な代金の支払いをしなくてはならないケース。
このとき、任意後見人は親(本人)の契約行為を取り消してなかったことにすることはできません。
一方で、法定後見制度であれば、上記のようなケースにおいて後見人に取消権が認められています。
死後の財産管理や事務は依頼できない
親(本人)が死亡した時点で、任意後見契約は終了となります。
つまり、死後事務(身辺整理など)や財産管理を任意後見人に依頼することはできません。
死後事務を依頼したい場合は、別途、死後事務委任契約を締結する必要があります。
任意後見契約でカバーできるのは、あくまで親(本人)の生存中の財産管理に限るという点が注意です。
任意後見制度を活用することで、親が認知症になった場合でも安心して財産管理を行うことができますが、その特性と注意点をしっかり理解しておくことが大切です。
【任意後見制度】メリットデメリットまとめ
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 自分の意思で後見人を選定できる | 第三者の後見人は費用が高い |
| 契約内容の自由度が高い | 任意後見監督人の選任が必要 |
| 生活支援の範囲や方法も事前に合意できる | 後見人に取消権がない |
| 後見人に支払う毎月の報酬も自由に設定できる | 死後の財産管理や事務は依頼できない |
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
法定後見制度の特徴とメリット・デメリット
親が認知症になった場合に考えられるもう一つの財産管理方法として、法定後見制度があります。
これは家庭裁判所が後見人を選任し、親の財産管理を行う制度です。
この法定後見制度の特徴とメリット、デメリットを見ていきましょう。
法定後見制度のメリット
法定後見制度のメリットは、公正さと法的な保護が確保されることです。
家庭裁判所が後見人を選ぶため、親の利益が守られる仕組みが整っています。
つまり、「親にとって」は安心・安全な制度です。
また、後見人の活動は定期的に報告され、裁判所の監督を受けるため、不正行為のリスクも低減されます。
さらに、任意後見制度では「後見人に取消権がない」ことに触れましたが、法定後見制度には取消権があります。
そのため、親(本人)が不利益な契約をしてしまった場合でも取り消すことが可能です。
法定後見制度のデメリット
一方で、法定後見制度にはデメリットもあります。
親(本人)や家族が希望する法定後見人にならない可能性がある
法定後見人は家庭裁判所が選任するため、親(本人)や家族が希望する法定後見人にならないことがあります。
親族を法定後見人の候補者として申し立てをしても、最終的には家庭裁判所の判断となるのです。
親(本人)の所有財産が高額
家族・親族間にトラブルがある
上記のような場合特に家庭裁判所は、法定後見人を法律の専門家である弁護士や司法書士を選任することが多いです。
家族以外が法定後見人になった場合のデメリットは多岐にわたります。
ランニングコストが高い
法定後見人へ支払う費用は月額2万円から6万円程度が相場とされています。
上記金額はあくまで固定報酬となり、それ以外に「付加報酬」が必要になります。
付加報酬とは親(本人)の税務申告や相続手続きが必要な場合に都度発生します。
財産の自由な活用・積極的な運用や移動ができなくなる
法定後見制度は、前述したとおり、「親にとって」は安心・安全な制度です。あくまで、本人の財産を保護する視点が中心になります。
そのため、家族や親族が本人のために資産運用をしたいと考えてもすることができません。
特に、不動産活用や株式投資などの元本が保証されないようなリスクがある行為は禁止されています。
公的介入が大きいためプライバシー保護に懸念がある
家庭裁判所や法定後見人に選定された士業(弁護士や司法書士)とのやり取りが多く、プライバシー保護の観点から選択しづらい制度となっています。
途中で法定後見人を解任できない
こちらも法定後見制度の大きなデメリットです。
正当な理由がない限り、親(本人)が死亡するまで法定後見人を解任できません。
仮に法定後見人を解任できたとしても、別途、新しい法定後見人が選定されます。
つまり、制度自体、途中で中断することができないのです。
ここでランニングコストを思い出してみてください。
法定後見人に毎月3万円を支払うとします。年間36万円。
10年で360万円。
上記以外に「付加報酬」も発生します。

どの制度が良いか分からないから、とりあえず法定後見制度が良いかな。。。
一番しっかりしてそうな制度の名前だし。
よく分からなくても弁護士さんがやってくれるし。
こんな軽い気持ちで選択すると思いもよらないコストに苦しめられるかもしれません。
法定後見人によっては。。。
法定後見人は、毎月の収支報告や財産管理の状況を裁判所に年に1度報告しなければなりません。
昨今では、法定後見制度の利用が増加しており、家庭裁判所での管理監督が行き届いていないケースが増えてきています。
そうなるとどうなるか?
なんと、法定後見人になった弁護士や司法書士による不正が出てきてしまっているのです。
また、不正でなくても法定後見人の権限は非常に大きく、親(本人)を取り巻く家族が困るケースが発生します。
金銭の借り入れ
重要な財産の売買
相続・贈与
大規模修繕
親(本人)の生活のためや、今後の家族のためにしておきたい上記のようなケースも大きな制限があり、家族にとっては不満に思うこともあるかもしれません。
【法定後見制度】メリットデメリットまとめ
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 公正さと法的な保護が確保される | 親(本人)や家族が希望する法定後見人にならない可能性がある |
| 身近な人による財産の使い込みを防げる | ランニングコストが高い |
| 不利益な契約を取り消せる | 財産の自由な活用・積極的な運用や移動ができなくなる |
| 公的介入が大きいためプライバシー保護に懸念がある | |
| 途中で法定後見人を解任できない | |
| 法定後見人によっては不正リスクがある | |
| 法定後見人によっては不当な制限を感じることがある |
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
家族信託の特徴とメリット・デメリット
最後の紹介するのは家族信託です。
家族信託はいま、親が認知症になった場合の財産管理方法として非常に注目されています。
この方法は、親が信頼できる家族に財産を託し、管理を任せる仕組みです。
親の希望を細かく反映できるため、柔軟な財産管理が可能です。
ここでは、家族信託の特徴とメリット、デメリットについて詳しく見ていきましょう。
家族信託のメリット
まずはメリットから見ていきましょう。
親(委託者)の意思能力の有無に財産管理が影響されない
家族信託を行うと、認知症による資産凍結に備えることができます。
信託財産は受託者の名義で管理されるため、親が判断能力を失ってもスムーズに運用が継続されます。
なぜなら、託者の財産の所有権が受託者に移転するためです。
柔軟な財産管理ができる
家族信託は財産管理の柔軟性もメリットです。
信託契約に基づき、親の意向を細かく反映させることができます。
特定の資産の運用方法や分配方法など、親の希望に合わせた管理が可能です。
例えば、法定後見制度では制限されていた積極的な資産運用も家族信託であれば可能です。※あくまで余剰資金での運用です。
不動産の売却についても法定後見制度では家庭裁判所の許可が必要ですが、家族信託では、予め信託契約に盛り込んでおくことで家庭裁判所の許可は不要となります。
そのため、手続きの手間やスご家族のストレスも削減でき、スムーズな財産管理が実現できます。
遺言としての機能がある
家族信託は「遺言」の機能があります。
親(本人)が死亡してしまった後に財産を引き継ぐ人を信託契約書の中で指定することができるからです。
そうすることで、親(本人)が亡くなってしまった後も親(本人)の生前、財産の管理を任されていた人の下で、そのまま財産の管理が可能となります。
注意点としては、あくまで家族信託は「信託財産」についての取り決めであるということ。
つまり、信託財産以外の承継先については、別途遺言書の作成が必要になります。
相続による遺族の負担が軽減される
財産の承継者やその内容を信託契約で適切に定めておくことで、遺産分割協議を行う必要がなくります。
遺産分割協議では、相続人全員で話し合い、誰が何を相続するのかを決めなくてはいけません。
しかし、相続人の間で意向を揃えることは容易ではありません。兄弟の数、相続人の数が多ければ多いほど意見がまとまらないでしょう。
また、相続人の誰かが認知症などで意思能力を欠いている場合は、成年後見人を立てなければ遺産分割協議自体が行えません。
財産を渡す側の親(本人)が財産の承継についてあらかじめ決めておくことで家族の負担やトラブル回避ができるのです。
この部分は家族信託の最もメリットのある部分かもしれません。
不動産などの共有財産のトラブル回避ができる
不動産などの共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなることで、よいタイミングで有効活用や処分ができなくなるリスクを回避できます。
例えば不動産。
兄弟3人でひとつの不動産を共有しているケースを考えてみましょう。持ち分はそれぞれ3分の1ずつ。
この場合、だれか1人が認知症で判断能力がなくなってしまった場合、不動産の有効活用や売却自体ができなくなってしまいます。
3人での共有なので3人全員の契約能力が必要だからです。特に兄弟全員が高齢化していると注意が必要と言えます。
このようなトラブルはあらかじめ財産を承継する方々の中で決めていなかったことが原因です。
家族信託ではあらかじめ財産を管理する人を指定できるため、このようなトラブルが起こるリスクを減らせきます。
倒産隔離機能がある
「倒産」という言葉を聞くとなにか事業に関わる問題?と思うかもしれませんがそうではありません。
以下のようなケースです。

もし、受託者であるわたしがが破産をしてしまった場合に、信託した財産が差し押さえられちゃうの?

いえ、差し押さえられません。
信託した財産は、受託者であるあなたものではなく、あくまで財産権を持っている親のものです。
信託財産は、誰の固有財産でもない独立した財産として扱われるため、委託者や受託者の破産や債務の差押えの対象とはなりません。
ただし、親(本人)=受益者が差し押さえなどを受けてしまった場合、注意が必要です。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
家族信託のデメリット
ここからは、家族信託のデメリットを見ていきます。
受託者の責任・負担が大きい
信託法において、受託者には以下のような義務が定められています。
✅善管注意義務・・・善良な管理者として、細心の注意を払って信託事務を行う義務(信託法29条2項)
✅忠実義務・・・受益者のために忠実に信託事務を行う義務(信託法30条)
✅ 分別管理義務・・・信託財産を受託者自身の固有財産と分けて管理する義務(信託法34条)
✅信託事務を第三者に委託する際の選任・監督義務・・・三者に信託義務を委託した場合、適切な人選をし監督する義務(信託法35条)
✅帳簿等の作成・報告・保存義務 (信託法36条、37条)・・・信託財産に係る帳簿を作成し、受益者に対して貸借対照表、損益計算書について報告し、書類を一定期間保管する義務
う~ん。なかなか難しいですね。分かりやすい言葉に変えるとこんなイメージです。
✅善管注意義務・・・自分の財産を管理するとき以上に気をつけて信託財産を管理する必要がある。
✅忠実義務・・・受益者の利益になるように行動する必要があり、利益相反行為や競合行為をしてはいけない。
✅ 分別管理義務・・・自分の財産と信託財産は分けて管理する必要がある。
✅信託事務を第三者に委託する際の選任・監督義務・・・第三者に信託事務を委託する場合、適切な人を選ぶだけでなく、その後の監督もする必要がある。
✅帳簿等の作成・報告・保存義務 (信託法36条、37条)・・・年1回、決算書的なものを報告する必要があり、書類は10年保存する必要がある。
確かにこれだけ見るとかなりの労力と時間が必要なようです。
実務の専門的知識もないから、信託契約締結後に

こんなに大変だと思わなかった~~
となりそうですね。。。
家族信託できない財産もある
家族信託できない財産は大きく2パターンあります。
パターン1:信託契約から漏れた財産
当初の家族信託契約から外した財産、契約に入れ忘れた財産の承継はできません。
財産の承継を念頭に家族信託を利用する場合、信託できない財産を除いてすべて信託財産に含める必要があります。
ただこれは専門家でない限り、漏れを防ぐのはかなり難しそうですね。
パターン2:そもそも信託できない財産
そもそも信託できない財産が存在します。
ですが対策もあります。
①農地
農地法3条2項3号により、農地の信託はできません。
⇒対策 宅地転用の手続きを行えば信託可能。手続きには数ヶ月ほどかかることもあるため注要注意。
②預金債権
「〇〇銀行〇〇支店口座番号〇〇の預金」という名目での信託はできません。
⇒対策 「金銭」は信託可能なため、「金銭〇〇円」という形で信託契約書に記載。
③年金
本人の固有の権利(一身専属件)として与えられているため、信託財産にはできません。
⇒対策 年金受給口座から残高を信託用の口座に移行させ、金銭として信託する。
まず、信託契約の作成には専門的な知識が必要であり、弁護士や司法書士のサポートが必要になることが多いです。
親族間の不公平感を生む恐れがある
財産が一定量ある
仮に相続を考えた場合、相続人の対象が多い
このような場合、親(委託者)と子(受託者)だけで勝手に家族信託を進めてしまうと、知らされなかった家族や親族から文句が出てくることもあります。
受託者がお金を使い込んでいるのでないかという疑いが生まれ、家族間の大きなトラブルに発展することも。。。
対策は、あらかじめ家族信託を進める前にしっかり家族会議をしておくことが重要です。
委託者に契約の同意を取りにくい
委託者とは家族信託を契約して財産管理を受託者に依頼する人です。
つまり、祖父母や両親となります。
子供から親に

そろそろ家族信託しな~~い?
って簡単に切り出せないですよね?
仮に切り出せたとしても家族信託の内容をうまく伝えられるかどうか?
聞きなれない契約ごとですし、不安や勘違いが起こって話が進まないこともあるでしょう。
費用がかかる
当然、家族信託の契約には費用がかかります。
具体的にかかる費用はこちら。主にかかるのは初期費用となります。
信託内容や手続きのコンサルティング費用・・・信託財産の1%程度
家族信託契約書作成費用・・・10~15万程度
登記手続きの代行費用・・・5万~15万程度
家族信託契約書を公正証書化する費用・・・15万~25万程度
不動産も信託する場合・・・信託不動産の固定資産税評価額の0.3%〜0.4%
初期費用でおよそ30万~60万程度かかります。
上記は初期費用なので、これ以外にランニングコストも少額ですが発生します。
ここで、家族信託と成年後見制度の費用を比較してみましょう。
| 家族信託 | 成年後見制度 | |
| 初期費用 | 30万~60万 | 20万 |
| 月額費用 | 約2,700円 | 2万~6万 |
家族信託の月額約2,700円はランニングコストとして破格ですね!
初期費用は家族信託のほうが高いですが、長い目で見ると圧倒的に家族信託のほうがメリットがあると言えます。
【家族信託】メリットデメリットまとめ
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 親(委託者)の意思能力の有無に財産管理が影響されない | 受託者の責任・負担が大きい |
| 柔軟な財産管理ができる | 家族信託できない財産もある |
| 遺言としての機能がある | 親族間の不公平感を生む恐れがある |
| 相続による遺族の負担が軽減される | 委託者に契約の同意を取りにくい |
| 不動産などの共有財産のトラブル回避ができる | 費用がかかる |
| 倒産隔離機能がある |
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
家族信託が最適な理由
認知症の親の財産管理の方法として
の3つのメリットデメリットを見てきました。
その中でもわたしは家族信託が圧倒的におススメです。
シンプルにメリットが一番多い
家族信託がおススメの理由としては、そのメリットの多さです。
デメリットを軽減する方法がある
なにより特筆したいことは家族信託のデメリットを軽減する手段があるということです。
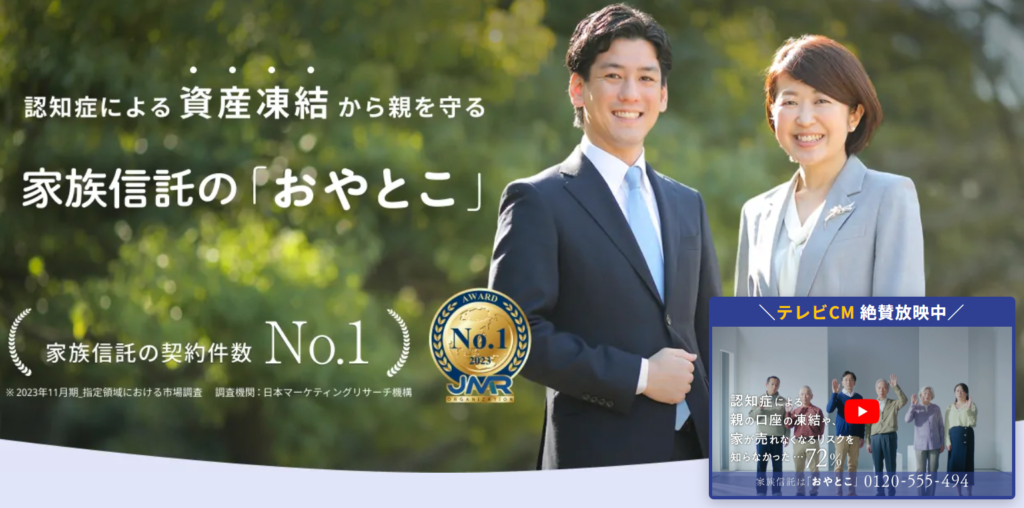
引用:家族信託のおやとこ
家族信託の「おやとこ」なら、家族信託専門の司法書士がサポートしてくれます。
2016年から家族信託サポートを続けており、契約数NO.1、サービス満足度96%で安心です。
デメリットに挙がっている点はほぼおやとこが解決してくれます。
✅受託者の責任・負担が大きい
⇒家族信託専用アプリで帳簿や報告書を自動生成や専門家へのタイムリーな相談が可能です。
✅親族間の不公平感を生む恐れがある
✅委託者に契約の同意を取りにくい
⇒おやとこが両親や家族への面談にも同席して、家族全員が納得するまで説明をしてくれます。
相談料や着手金は発生しません。
✅費用がかかる
⇒家族信託専用アプリは月額たったの2,728円!
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
家族信託を導入した際のストーリー
親が認知症を発症する前に家族信託を設定し、信頼できる子供が受託者となります。
そうすると、親が判断能力を失った後も、スムーズに財産の管理と運用が続けられます。
親の希望通りに資産を運用でき、必要な介護費用や生活費も問題なく支払うことができます。
イメージが沸きますでしょうか?
このように、家族信託は実際のところすでに多くの家庭で導入されており、安心して利用できる方法です。
家族信託の始め方
家族信託は、親が認知症になった場合でも安心して財産管理を行うための有効な方法ですが、初めて家族信託を導入する際には、どのような手続きが必要かを理解することが重要です。
以下では、家族信託の契約手続き、その他の必要な書類について説明します。
家族信託の契約手続き
家族信託を始めるためには、まず信託契約を結ぶ必要があります。
この契約は、親(委託者)が自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託す内容を明記します。
契約内容には、財産の管理方法、受益者(財産の利益を受ける人)、信託の期間などが含まれます。
信託契約は、公正証書として公証人役場で正式に作成します。
これにより、契約の法的効力が確保されます。
その他必要な書類
親の身分証明書や受託者の身分証明書も必要です。
これらの書類は、信託契約の正当性を確認するために使用されます。
さらに、信託財産の詳細を記載した書類も必要です。これには不動産の登記簿謄本や金融資産の明細書などが含まれます。
前述していますが当初の家族信託契約から外した財産、契約に入れ忘れた財産の承継はできません。
財産の承継を念頭に家族信託を利用する場合、信託できない財産を除いてすべて信託財産に含める必要があります。
ただこれは専門家でない限り、漏れを防ぐのはかなり難しそうですね。
専門家のサポートを受けるべき
信託契約書や信託財産の詳細を記載した書類を説明してきましたが

これを自分でやるなんて絶対ムリ!
専門家にお願いするしかない!
というのが結論だと思います。
この記事を書いているわたしも実際に家族信託を進める場合、即、専門家に相談します!
弁護士や司法書士などの専門家は、信託契約の内容を法的に適切に作成するためのアドバイスをしてくれます。
専門家のアドバイスを受けることで、親(本人)の希望に沿った契約内容を確実に反映させることができますし、専門家が信託契約の手続きをサポートしてくれるため、スムーズに進めることができます。
ただし、専門家は費用が見えにくいうえ、初期費用以外のサポート(月額料金)もお願いすると費用が高くなってしまいます。
専門家であり費用が抑えられる選択肢。。。それがおやとこなんです。

引用:家族信託のおやとこ
家族信託の「おやとこ」なら、家族信託専門の司法書士がサポートしてくれます。
2016年から家族信託サポートを続けており、契約数NO.1、サービス満足度96%で安心です。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
まとめ・家族信託のよくある質問
いかがでしたでしょうか?
家族信託は、数ある財産管理の方法の中でも、信頼できる家族に財産を託し、親(本人)の意向に沿った柔軟な管理が可能な方法です。
信託監督人の設置により、公正な運用が確保されるため、親も家族も安心して財産を管理できます。
認知症の兆候が見られる前に早期の対策を講じて、親の財産を守り、安心して暮らせる環境を整えましょう。
家族信託は、そのために最適な方法です。
家族信託とは何ですか?
家族信託は、親が信頼できる家族に財産を託し、その管理や運用を任せる仕組みです。
親が委託者、信頼できる家族が受託者、そして財産の利益を受ける人が受益者となります。
家族信託のメリットは何ですか?
家族信託のメリットは、柔軟な財産管理が可能なこと、親の希望を反映した運用ができること、そして信託監督人の設置により公正な管理が確保されることです。
家族信託はいつ始めるべきですか?
家族信託は、親が判断能力を失う前に始めることが重要です。
早めに準備することで、親の希望をしっかり反映した契約を結ぶことができます。
家族信託のデメリットは何ですか?
デメリットとしては、契約作成に専門家のサポートが必要であること、初期費用や手続きに時間がかかること、そして受託者に大きな責任が伴うことが挙げられます。
家族信託を始めるには何が必要ですか?
家族信託を始めるには、信託契約書の作成、親と受託者の身分証明書、信託財産の詳細を記載した書類が必要です。
これらの書類を公証人役場で公正証書として作成します。
信託監督人は必ず必要ですか?
信託監督人は必須ではありませんが、設置することで受託者の行動が監督され、公正な管理が確保されるため、信託の安全性が高まります。
家族信託と後見制度の違いは何ですか?
家族信託は親が自分の意思で財産管理を委託できる方法で、柔軟性があります。
一方、後見制度は家庭裁判所が後見人を選任し、親の判断能力が低下してから管理を行う方法です。
▽相談だけでもOK!電話でもメールでもどちらでもOK!全国対応OK!
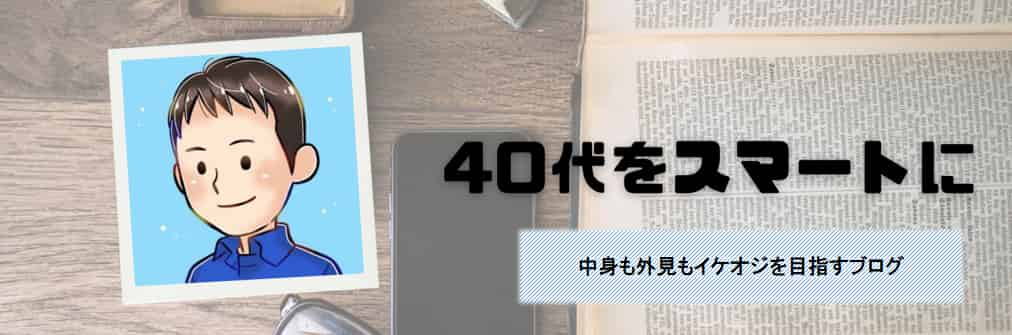






コメント