近所の方とすれ違ったとき、あいさつができない子どもにがっかりしたり、腹を立てたりしていませんか?小学生なのに、あいさつをするように何回言ってもできない・・・
「あいさつができるように教える方法」「子どもが進んであいさつをするようになる方法」がネットやYouTubeに溢れていますが、どれも具体性に欠けます。
この記事では子どもがあいさつをするようになる具体的なコツとルールをお伝えします。
あいさつができない小学生を持つお父さん・お母さん必見です。
はじめに私についての紹介です。詳細はプロフィールをご覧ください。

運営者:すくらっち
【主体性を育む演出家】40代2児の父 | 子育て10年 | 管理職10年 | 管理職として培った「自ら考え行動する人材育成術」を子育てで実践→思い通りにならないイライラから開放→人生の充実感が増す | 管理職にも子育てにも実践できる育成テクニックを発信中 | 主体性ある人は輝いている。輝く人を育てることが私の最高の喜び
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しております。※
▼子どもの主体性を育む方法はこちら
小学4年生 5年生 6年生こそ見直したい【自主学習】のやり方は小学生のうちに身につけよう
プログラミング学習スクール【みらいごとラボ】の評判は?実際に子どもが受講してみた感想
【小学生のお小遣い】相場や平均金額は?子どものお小遣いに報酬制を取り入れる
具体的な3つのコツ
あいさつができない理由はおおきく2つだと考えています。
①恥ずかしい、人見知り ②タイミングがつかめない
これに対して改善する方法は以下の3つです。
あいさつをする理由を理解させる
あいさつをする対象・範囲を明確に伝える
予めシチュエーションを想定して準備とルールを決めておく
ひとつずつみていきましょう。
あいさつをする理由を理解させる

目的を明確にする
子どもにあいさつをしなさいとは言いますが、なんであいさつをする必要があるのか伝えたことはありますか?あいさつをしないとどんなデメリットが生まれるか教えていますか?ここをしっかり子どもが理解していないのが一番の原因です。
目的が理解できていないため、行動だけ強制しても思考停止してしまっています。思考停止してしまっているので、何度行動を促してもなかなか身につきません。
進んで行動する(あいさつする)ためには目的(あいさつする理由)を明確にする必要があります。
あいさつをするメリット
あいさつをする理由を掘り下げて、あいさつをするメリットを洗い出しましょう。
円滑なコミュニケーションを生み出す
礼儀正しさ、誠実さを伝えられるため信頼を得ることができる
自分が困っているとき助けてもらえる関係を構築できる
大きくこのあたりだと思います。3つとも将来子どもが大人になったとき、ビジネスシーンで重要な要素ですよね。子どものうちからこういうメリットがあることを理解させましょう。ただ、上記の言葉で伝えてもピンとこないと思います。以下のように伝えてみるのはいかがでしょうか?
◆あいさつをした人もされた人もうれしい気持ちになって幸せが寄ってくるよ。
◆あいさつができてエライ!って思ってくれたり、言ってくれるようになる。やさしく接してくれるようになるし、なにか〇〇ちゃんが(子どもの名前)困っているときに助けてくれるよ。
あいさつをしないデメリット
動機を持たせる手段としてデメリット(危機感)を伝えることも効果的です。
◆あいさつするのが恥ずかしいかもしれないけど、あいさつできないほうが恥ずかしいって思われてるよ
◆あいさつできないと、感じ悪いって思われて〇〇ちゃんが(子どもの名前)困っているときに助けてくれないよ。例えば、転んでけがして泣いていても声かけてくれないし、悪そうな人が○○ちゃんを誘拐しようとしてるのを見ても、知らんぷりされちゃうよ。
あいさつをする対象・範囲を明確に伝える

子どもは線引きが分からない
これができていないお父さん・お母さんが非常に多いです。あいさつについてまだ勉強中の子どもが親があいさつをしている姿をみてきっとこう思ってます。

・さっきすれ違った人にはあいさつしたのに、今すれ違った人にはあいさつしてない。
・なんだ。あいさつってしたいときにすればいいのかも。
・ママもあいさつしないときがあるし、ぼくもしなくても良いよね。
つまり「あいさつをする人、しない人」の線引きを明確に理解していないため、子どもは間違った解釈をしているのです。
あいさつをする対象・範囲は?
明確に教えてあげてください。ぼんやりした表現だと伝わりませんし、あいさつができない状況から抜け出せません。参考にわたしが小学生の子どもに伝えている線引きラインを紹介します。
・親族(じいじ、ばあば、いとこ家族など)
・マンション内で会う人(郵送関係の人は除く)
・学校の先生・学校の友達とその家族
・お父さん・お母さんの知り合い(どういう知り合いなのか都度説明する)
こうすることで、全く知らない人にあいさつをして犯罪に巻き込まれるようなリスクを排除することにもつながります。
予めシチュエーションを想定して準備とルールを決めておく

子どもがあいさつをすることに慣れてくるまでは、しっかり家庭内で準備をしましょう。準備といっても、あいさつが必要になるシチュエーションを想定して「こういう時はどうする」というルールを事前に決めておくだけです。わが家の6か条を紹介します。
①「おはようございます!」か「こんにちわ!」の2択にしておく
(小学生の行動時間的に「こんばんは!」は頻度が低いため)
②誰にどこで会うケースが多いか家庭で話をしておく
③あいさつをする対象者を見かけたら自分からあいさつをする
④あいさつをする対象者かどうか迷ったらとりあえずあいさつをする
⑤向こうからあいさつをされたら必ずあいさつを返す
⑥お父さん・お母さんがあいさつをしたら続けてあいさつをする
できないことを叱るよりできたときに褒めよう
以上、3つの方法について紹介しました。さっそく明日から実践してみてください。ですが、実施してもすぐに身につくものではありません。3つの方法を実践していたら少しづつ変化してきますので暖かく見守ることが重要です。
お父さん・お母さんにお願いしたいことは、あいさつができなくても叱らない、あいさつができたら褒めてあげてください。
叱ると子どもは委縮してしまってますますあいさつしにくくなります。とても悪循環です。
あいさつができなくても「次は頑張ろうね」と軽く声をかける程度。
あいさつができたら「すごいね!ママびっくりしちゃった!」を必要以上に大げさに褒めてあげましょう。
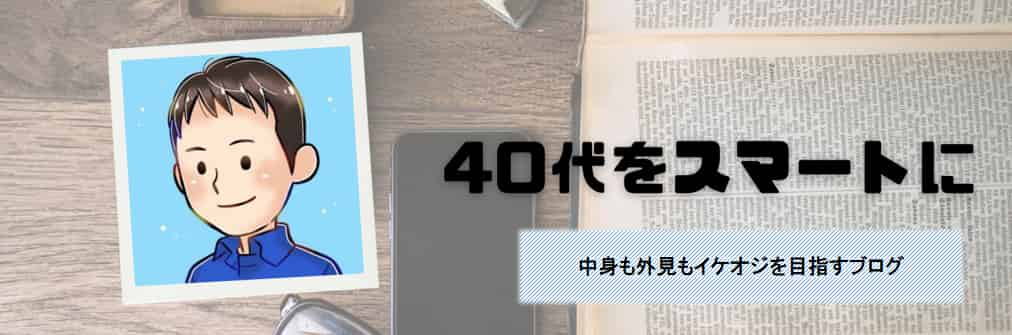
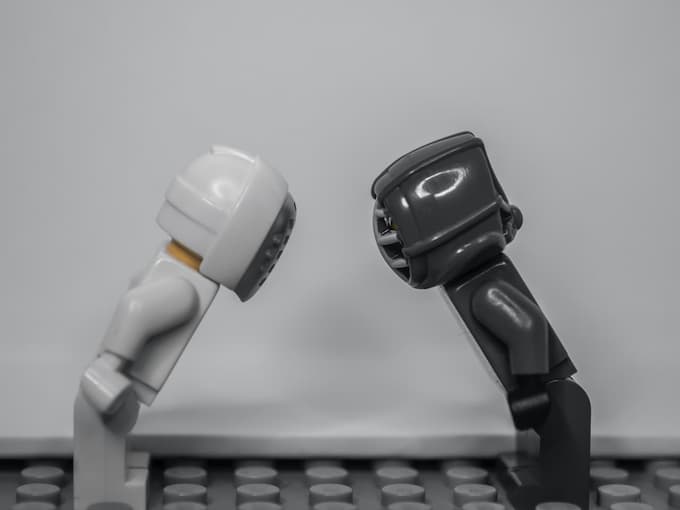


コメント